「Super jury Program Winter 07」レポート
07.01.20
1/19、東海大学秋セメスター総合講評プログラムが開催されました。毎年の事ですが、一般的には上位に上がってくる学生はいつも決まっていて、名前や顔も覚えていますから毎年成長していくのが見れて楽しい一方で、昨年まで優秀だった学生が、今年は発表の機会を与えられず参加していない状況もあるのも確かです。私は1年後期から2年前期を担当していますが、その間というのは、課題に求められるプログラムの比較的単純で、直球勝負で(つまり感性最優先で)勝負が決まりやすく、学生も延び延びと楽しそうにやっており、優秀な学生もほぼfixされている印象があります。ところが、2年の後期から3年になると、いよいよ求められるプログラムや制度上の規制など、直球勝負では解く事が難しい課題が与えられ、いままで上位に上がって来なかった学生が上位に上がってきたりします。どちらも建築を構築するには必要不可欠な才能でしょうが、残念なのは課題が難しくなって行くに従って、設計の授業を履修する学生数も加速度的に減ってきてしまうところです。感性だけでは課題は解けない、と分かったらさっさと設計を投げ出してしまうのでしょうか。
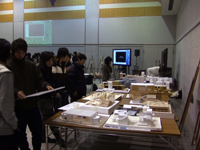 2年生くらいまではとても素晴らしい感性が表現できていたとしたら、それはとても残念な事です。ともかく、総合講評会は多くの専任+非常勤の先生達によって(実際学生と同数くらいだった)熱く批評され意義ある時間でした。一番元気がなかったのは修士の学生。これは毎年の傾向ですが、どうしてかな。
2年生くらいまではとても素晴らしい感性が表現できていたとしたら、それはとても残念な事です。ともかく、総合講評会は多くの専任+非常勤の先生達によって(実際学生と同数くらいだった)熱く批評され意義ある時間でした。一番元気がなかったのは修士の学生。これは毎年の傾向ですが、どうしてかな。










