Super Jury Program Winter 2012
12.01.23
東海大学建築学科の総合講評会が先日行われ、今年度の授業もこれで終了しました。改めて思うのですが、総合講評会のいいところは全学年を通じて先輩後半の優秀作品を見ることが出来ることと、担当ではなかった先生の意見を聞けるところにありますので、学生にとってはいい経験だと思います。
 昨年同様、今年も印象にのこったことは、高学年になるほどに説明していることの意味がよく分からない、ということです。もちろん内容は難しくなるわけですが、それ以上に問題なのは専門用語の乱用でしょう。しかもその本人がどうやら意味を分からずに使っている気がしてなりません。自信が無いのか妙に早口だし、台詞を用意している大学院生も珍しくありません。誰かの受け売りの言葉であった場合、その言葉の意味や奧に隠された本質まで思いを馳せることが出来ず、説明そのものが軽薄になってしまいます。別に建築に限った話では無いのですが、我々は常に素人を相手に話しをする商売だと思っています。どんな人にでも、可能な限り我々の思想やその結実としての空間を伝える義務があります。どんな些細なことでも、その本質をより正確に他者へ言葉を用いて伝達することの難しさは、実際に社会で出ると分かるはずです。
昨年同様、今年も印象にのこったことは、高学年になるほどに説明していることの意味がよく分からない、ということです。もちろん内容は難しくなるわけですが、それ以上に問題なのは専門用語の乱用でしょう。しかもその本人がどうやら意味を分からずに使っている気がしてなりません。自信が無いのか妙に早口だし、台詞を用意している大学院生も珍しくありません。誰かの受け売りの言葉であった場合、その言葉の意味や奧に隠された本質まで思いを馳せることが出来ず、説明そのものが軽薄になってしまいます。別に建築に限った話では無いのですが、我々は常に素人を相手に話しをする商売だと思っています。どんな人にでも、可能な限り我々の思想やその結実としての空間を伝える義務があります。どんな些細なことでも、その本質をより正確に他者へ言葉を用いて伝達することの難しさは、実際に社会で出ると分かるはずです。
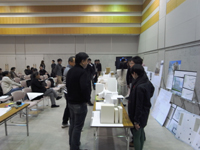 専門用語を使うことの安直さは、例えば平面図に登場する「リビング」や「ダイニング」、あるいは「和風」とか「モダン」とかに似ていると思います。それらは決して専門用語とは言えず既に誰もが知っている言葉です。が、「知っている」とは本当はどこまで「知っている」のか実は誰も分からないのです。分からないにもかかわらず「知っているだろう」という妙な前提から会話は進行していきます。それがつまり形式とかスタイルと呼ばれるもので、本当は何だからよく分からない事柄を一言でまとめ上げてしまう言葉であり、その安易さで社会は滞りなく廻っていくものなのです。
専門用語を使うことの安直さは、例えば平面図に登場する「リビング」や「ダイニング」、あるいは「和風」とか「モダン」とかに似ていると思います。それらは決して専門用語とは言えず既に誰もが知っている言葉です。が、「知っている」とは本当はどこまで「知っている」のか実は誰も分からないのです。分からないにもかかわらず「知っているだろう」という妙な前提から会話は進行していきます。それがつまり形式とかスタイルと呼ばれるもので、本当は何だからよく分からない事柄を一言でまとめ上げてしまう言葉であり、その安易さで社会は滞りなく廻っていくものなのです。
 皆が皆、いちいちそんな日常語にいちゃもん付けていたら会話が成り立ちませんから。しかし、プロはそうであってはいけません。例えるならば、「リビング」「ダイニング」という言葉を一切用いずに平面を計画し、クライアントに説明出来るかどうか、です。専門用語を使わないと腹をくくった時から、事の本質を考えざるを得なくなります。少なくともacaaではいつもそう考えながら仕事しています。
皆が皆、いちいちそんな日常語にいちゃもん付けていたら会話が成り立ちませんから。しかし、プロはそうであってはいけません。例えるならば、「リビング」「ダイニング」という言葉を一切用いずに平面を計画し、クライアントに説明出来るかどうか、です。専門用語を使わないと腹をくくった時から、事の本質を考えざるを得なくなります。少なくともacaaではいつもそう考えながら仕事しています。









